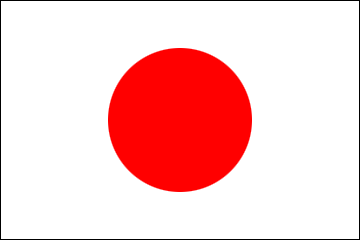JICAボランティアエッセイ(籠谷JV)
令和元年6月20日
パラオからの手紙
籠谷 啓史
僕は今、マルキョク州にある本島唯一のカフェでこのレポートを書いています。
2017年7月、マルキョク小学校・教員として活動を始めて2年。このカフェから広がるパラオの海、吹き抜ける風は変わらずに穏やかです。
その風を頼りにこの2年間を振り返ってみましょう。
きれいな海以外にとりたてて特色のない、マルキョク集落にある小学校が僕の活動地。活動内容は、(1)生徒の算数学力向上支援や、(2)教員の指導力向上支援です。
生徒の算数学力向上支援
生徒たちの学力は僕の想像以上でした。指を使って計算する低学年。九九のできない高学年。こんな子がたくさん。中には2+5を25と答える子まで・・・。日本とは全く違う生徒の学力に何度絶望したかわかりません。
「計算練習を繰り返せば・・」僕はそう考え、担当の先生(低学年)の同意を得て、計算問題の宿題を与え続けました。また3年生では、授業の冒頭時間を使って九九の練習を繰り返しました。休み時間には躓きがちな子への個別支援を継続しました。少しずつ少しずつ。「3歩進んで2歩下がる」どころではありません。時には「2歩進んでも3歩下がる」ことも。それでもほんの少しずつ、粘り強く坂をのぼっていきました。
数か月後、彼らは成長していました。九九をスラスラ言える子、繰り下がりの引き算を一瞬でできる子、指を使わずに計算する子。1日のステップはほんのわずかでも、それを積み重ねることでいつの間にか、ずっと先のゴールにたどり着いていたのです。「あきらめないこと」、「練習を続けること」それが多少なりとも形になってよかったと思います。
教員の指導力向上支援
非常に難しく、悩み、葛藤し続けた毎日でした。
1番の課題が「学習規律・授業規律」の問題でした。授業中、先生たちは気持ちよさそうに教壇で話し続けます。一方生徒たちは、そんな「聞くだけ」の授業にはすぐに飽きてしまい、お絵かき・おしゃべり・手遊びへ・・・。それでも先生たちはその子たちを咎めるでもなく、また話し続けます。僕は話を聞かせるための「しつけ」、授業に向き合わせるための「しかけ」の大切さを何とか伝えてみました。 ただ先生たちも人格形成された1人の大人。実践してもらうことは極めて困難でした。
「先生方の考え方・方針」、「先生方のプライド」、「個別の関係性構築」、「日本スタイルを押しつけないように」これらを全てクリアにして初めて、この課題は前に進みます。一つクリアしてもまた次のハードルが・・。全てをクリアすることは非常に難しく、自分の力不足を感じた2年間でした。
それでも何人かの先生は協力的で向上心もあり、実践を通じて指導力も向上しました。ほんのわずか成果ではありますが、この「技術移転」を前向きにとらえたいと思います。
こんなふうに取り組んできた2年間。成果や苦労に共通するのは「ソフト面」の大切さです。
僕が青年海外協力隊を志したきっかけの一つが、「途上国に学校を建てる」というテーマの映画でした。自分もこんな風に途上国の力になりたい。そんな思いでした。ただその映画は「学校を建てる」という「ハード面」にフォーカスしたもの。当然のことながら、ハード面だけでは本当の支援にはならないのです。その学校で生徒に有意義な学びを提供していくために、教員・教材・カリキュラム・運営等をいかに良質に高めていくか。これが学校支援におけるソフト面であり、その大変さと大切さを痛感した2年間でした。
ここでの経験は、これだけにとどまりません。異なる言語、異なる環境、異なる文化の中ですごしたパラオでの全ての経験。それは、僕のパレットに加わった新たな「絵の具」として自分を成長させてくれたような気がします。その絵の具は今度、いつ使うかはわからない。でも次の絵を描くとき、それが貴重なピースになるかもしれないからです。
僕に何かを促すように
風が一瞬やみました。
さあ、行きましょう。新たなキャンバスとなる次の舞台へ。