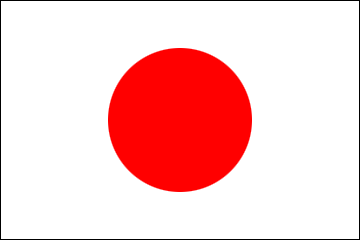JICAボランティアエッセイ(玉山JV)
平成30年9月13日
パラオの教育にふれて
玉山陽司
2年前、初めて日本を離れ、パラオで生活するようになった。海外旅行でさえしたことのなかった私にとって、正真正銘の初海外だった。しかし、国中で日本車が走っている光景や会話の中で聞こえてくる日本語に耳を傾けていると、自分が海外で生活しているのかどうか不思議に思うようになった。
私はパラオの田舎、ガラード小学校で2年間算数を教えてきた。この2年間算数の授業を作る時に常に考えていたことは、子供たち自身に、「自分はできるんだ」と実感させることだ。そのために、どういう説明の仕方をすれば分かりやすいか、どの教材を使えば理解が深まるかということを日々考えた。日本での教え方に拘らず、パラオの先生の指導法でいい点は積極的に活用した。その一つがパワーポイントを利用した授業である。パワーポイントを利用することによって、板書や作図の時間が短縮されたり、カラー写真が使えるようになったりした結果、子供たちの集中力が途切れないようになった。また、ノートに問題を解くよりも、プリントに問題を解く方が集中して取り組めていたので、授業の内容に合わせてプリントを作るようにした。勉強に取り組む姿勢が変わっていき、自信をもって勉強をするようになった。子供たちは本当に良く頑張ってくれたなと思う。問題が解けるまでしつこく子供たちに名前を呼ばれたことは、私にとっては彼らとの一番の思い出である。また、同僚の先生たちは私のことを信頼しいつも支えてくれた。コミュニティカレッジで学び直す先生や、遅くまで残って授業の準備をする前向きな先生の姿は私の刺激にもなった。先日は校長先生の提案で算数の公開授業に挑戦し、先生たちや私にとって非常によい経験になった。これからますます前向きな学校になっていってほしい。
ところで、驚かれるかもしれないがパラオには教員免許制度や教員採用試験といったものが存在しない。確かにこの現状が、教員の指導力に関係していることは明らかである。しかし、現実的な問題として、なり手が少ない現状ではそうした制度の導入は困難である。そのため、教育省は指導力向上のためにワークショップを行ったり、教員がコミュニティカレッジで学ぶことを推奨したりしている。私の配属先の同僚たちも、放課後ほぼ毎日コミュニティカレッジに通っている。また、公開授業を通して、先生たちが子供たちと悪戦苦闘しながら指導力を磨いている姿も見てきた。2年間こうしたそれぞれの形で課題を解決しようとしている人たちと関わってきて、改めて教育に携わる人たちの力強さを感じた。やはりその根底には、子供たちのよりよい将来のために働きたいという思いがあった。そういう人たちと2年間働けたことは、自分自身にとっても貴重な時間になった。
2年間、本当に多くの人たちが私のことを支えてくれた。パラオを発つ日が近づくにつれて、同僚たちは私の送別会についてパラオ語で時折話している。だいたいは食べ物の話なのだが、こうした雰囲気も恋しくなるだろう。残り短い期間だが、最後までパラワンスタイルを楽しみたい。
私はパラオの田舎、ガラード小学校で2年間算数を教えてきた。この2年間算数の授業を作る時に常に考えていたことは、子供たち自身に、「自分はできるんだ」と実感させることだ。そのために、どういう説明の仕方をすれば分かりやすいか、どの教材を使えば理解が深まるかということを日々考えた。日本での教え方に拘らず、パラオの先生の指導法でいい点は積極的に活用した。その一つがパワーポイントを利用した授業である。パワーポイントを利用することによって、板書や作図の時間が短縮されたり、カラー写真が使えるようになったりした結果、子供たちの集中力が途切れないようになった。また、ノートに問題を解くよりも、プリントに問題を解く方が集中して取り組めていたので、授業の内容に合わせてプリントを作るようにした。勉強に取り組む姿勢が変わっていき、自信をもって勉強をするようになった。子供たちは本当に良く頑張ってくれたなと思う。問題が解けるまでしつこく子供たちに名前を呼ばれたことは、私にとっては彼らとの一番の思い出である。また、同僚の先生たちは私のことを信頼しいつも支えてくれた。コミュニティカレッジで学び直す先生や、遅くまで残って授業の準備をする前向きな先生の姿は私の刺激にもなった。先日は校長先生の提案で算数の公開授業に挑戦し、先生たちや私にとって非常によい経験になった。これからますます前向きな学校になっていってほしい。
ところで、驚かれるかもしれないがパラオには教員免許制度や教員採用試験といったものが存在しない。確かにこの現状が、教員の指導力に関係していることは明らかである。しかし、現実的な問題として、なり手が少ない現状ではそうした制度の導入は困難である。そのため、教育省は指導力向上のためにワークショップを行ったり、教員がコミュニティカレッジで学ぶことを推奨したりしている。私の配属先の同僚たちも、放課後ほぼ毎日コミュニティカレッジに通っている。また、公開授業を通して、先生たちが子供たちと悪戦苦闘しながら指導力を磨いている姿も見てきた。2年間こうしたそれぞれの形で課題を解決しようとしている人たちと関わってきて、改めて教育に携わる人たちの力強さを感じた。やはりその根底には、子供たちのよりよい将来のために働きたいという思いがあった。そういう人たちと2年間働けたことは、自分自身にとっても貴重な時間になった。
2年間、本当に多くの人たちが私のことを支えてくれた。パラオを発つ日が近づくにつれて、同僚たちは私の送別会についてパラオ語で時折話している。だいたいは食べ物の話なのだが、こうした雰囲気も恋しくなるだろう。残り短い期間だが、最後までパラワンスタイルを楽しみたい。