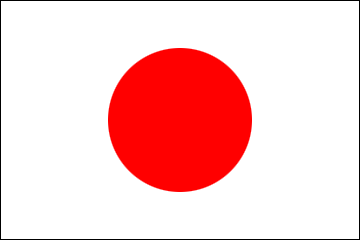パラオで活躍するJICAボランティア:荒木実佳子
平成28年12月15日



JICA ボランティア 荒木実佳子
Alii! パラオに住んで早くも二年が経とうとしています。幸せなことにホームステイ先の家族、配属先の同僚たちに恵まれ、パラオは第二の故郷と胸を張って言える場所になりました。大好きなパラオで私は何をしているかと言うと、コロール州政府の青少年部門で、青少年の健全育成に関する活動の企画をしています。二年間を通して沢山の人々に出逢い、「青少年」について考える日々を過ごしました。
日本とパラオの高校生を比較してみると、日本の高校生は非常に忙しい日々を過ごしているように感じます。夕方までの授業が終われば、部活動や塾で帰宅は21、22時になる学生も多くいます。対してパラオの高校生はどうでしょうか。「することがない」と言う声を何度か聞き、忙しすぎる日本の高校生と時間を持て余しているというパラオの高校生を比較せずにはいられませんでした。また、パラオに来て驚いたことは、高校生でもドラッグやマリファナなど違法薬物が簡単に入手出来てしまうことです。これまで取られた調査を見ても、また直接高校生に聞いてみても、違法薬物を見たことがある、使っている人を知っているなどの回答に驚きました。
そんな中同僚や高校生と話す中で、発見したことがありました。それは、私の配属先の青少年部門は男性が多いのですが、彼らと外に出ると、彼らの兄弟または親戚、近所の高校生が手を振ってきたり、”Obekuk!”と声を掛けるのです。初めは挨拶の言葉かと思っていましたが、年下の男性から年上の男性に対する敬称だったようで、時には相談に乗ったりしている同僚の話を聴きました。またパラオでは文化的に、母方の伯父(叔父)が甥や姪に対して責任があることにも驚きました。他にもAunty, Uncle, Rubakなど様々な呼びかけがありその時に、彼らのように”Obekuk”と呼べる人、つまり頼れる年上の人や大人がいることは青少年にとってとても幸運なことだと実感しました。青少年の悩みはとても複雑です。置かれている環境や周りにいる友人、家族など関わる人によって様々なストレスや悩みを抱えており、その内容も一人ひとり違います。そんな時に一人ひとりに誰か、心置きなく相談できる人、いつでも助けを求められる人がいれば、青少年に関する問題を減らすことが出来るのではないかと思います。
大人が問題視する青少年の問題を減らすには、まず大人が若者の声を聴くことです。それは日本も同じです。「~してはいけない」の視点から「どうして~するのか」に変え、彼らが抱える本当の問題は何なのかを、周りの大人が知ることが最優先です。
皆さんにはObekukのように頼れる人はいますか?もちろんあなたを必要としている人もいます。もう一度人とのつながりを見直し、人が人を育てる社会へとパラオが発展していけることを願い、残りの二ヶ月も活動に尽力したいと思います。